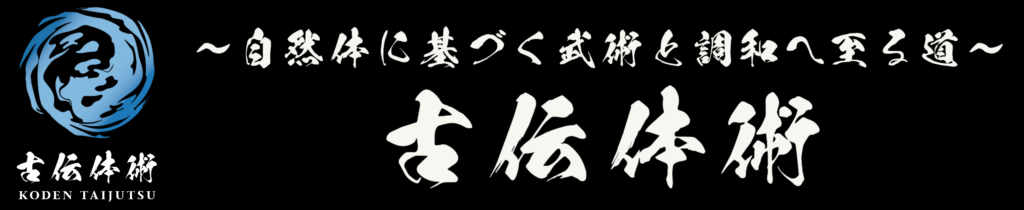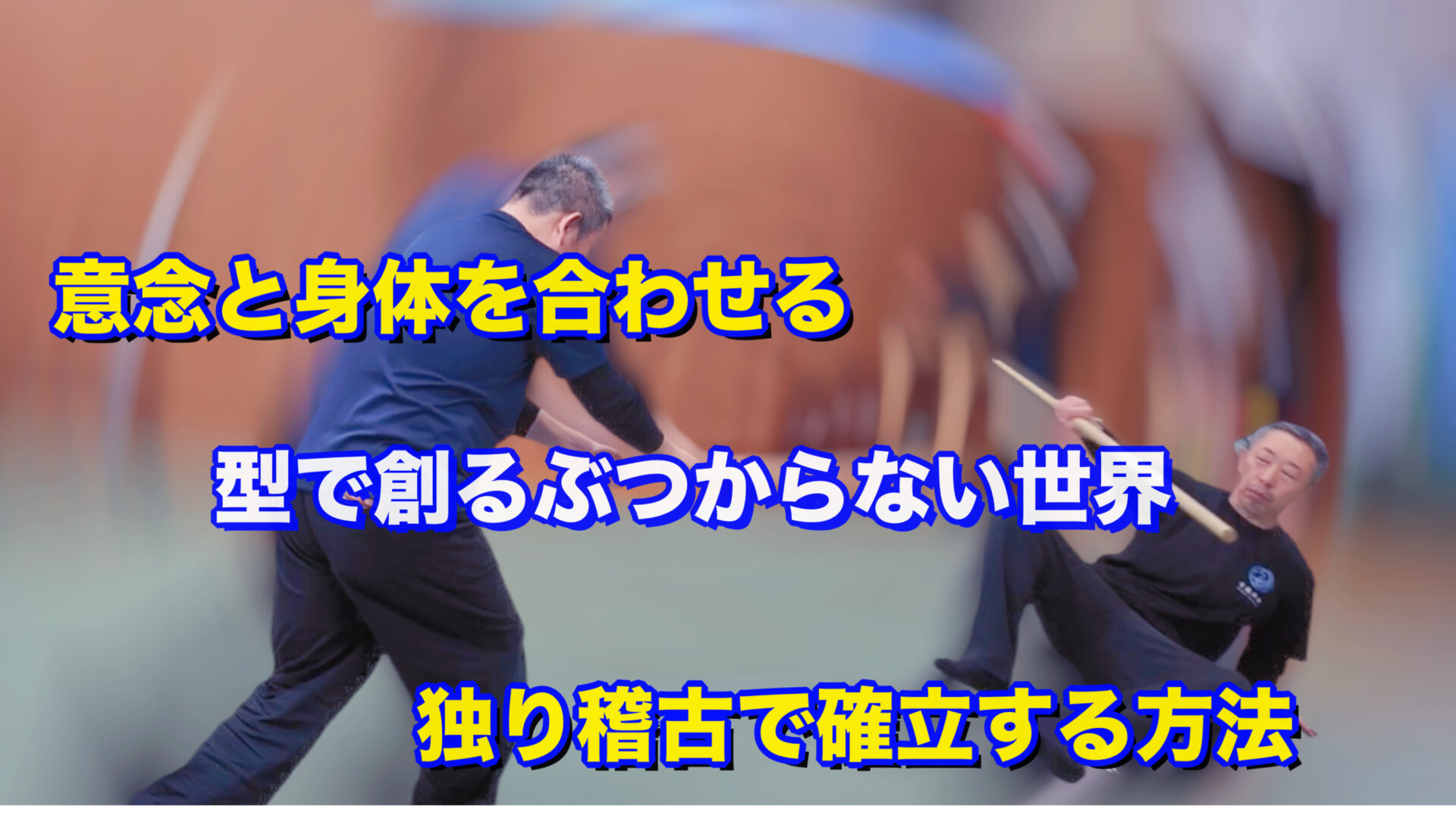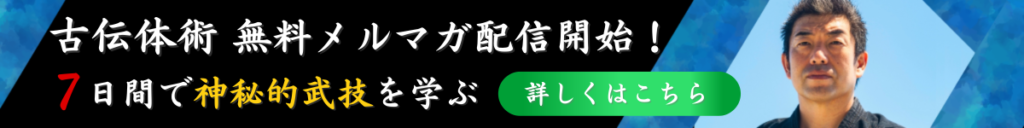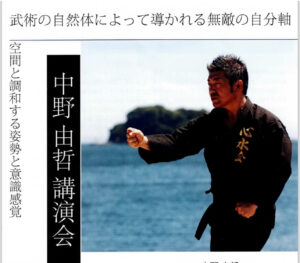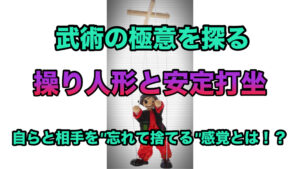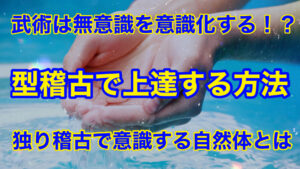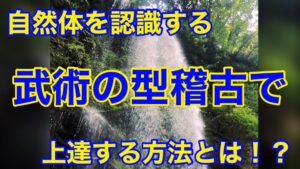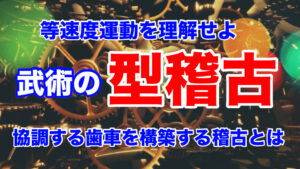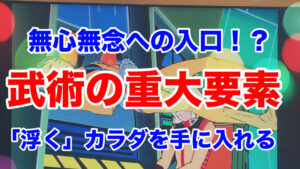古伝体術の中野です。
最近は「ぶつからない和の武術操法」という感覚に基づき稽古しています。
「ぶつからない和の武術操法」とは果たして何なのか?
それについては色々な考え方があるかと思いますが、古伝体術では
浮身 順体 等速度運動 螺旋
などを保つことによって、「ぶつからない
世界を体現する身心のあり方」
と、考えております。
例えば
「抜刀動作」
というもので考えてみます。
日本人でも「刀を抜く」という行為に触れたことがある人は意外と少ないのではないでしょうか。
女性はなかなか刀というものに興味を持つことがないと思うので、当然といえば当然ですが、男性でも抜刀動作や納刀動作を経験した人というのは案外少ないと思われます。
また、何かしらの武道や武術を経験してる人でも、武器を扱うことのない柔道や空手などの体術主体で稽古されてる方も刀、つまり「日本刀」というものに触れる機会はなかなかないと思われます。
最近では、テレビ番組や映画でも時代劇というものが、制作されることが少なくなり、
益々、日本刀との繋がりみたいなものが薄くなってきているように思われます。
実際に行ってみるとわかりますが、抜刀動作をしたことがない人が、
左腰に帯刀した状態から刀を抜こうとしても
鞘から刀の切っ先ができきらずに刀を抜くことが出来ない。
このようになることが多いです。
これは、左腰に帯刀した刀を右手だけを用いて抜こうとするために
起きる現象となります。
そのようにならないために「鞘引き」という左手の使い方が必要となってくるのです。
つまり、抜刀するためは右手と左手を連動して動かすということが必要であり、身体の一部だけを動かすのではなく、あくまでも全身のつながりがある中で連動して動かす必要がある。
そこを学べるようになっているのです。
空手などでは、右手と左手が連動して動くようにすることを
「夫婦手」
という言葉で表現しております。
空手の基本の突きの動作において、「突き手」と反対側は「引き手」となっており
右手と左手が助け合うように動いています。
これにより、全身が連動して動く感覚を養成しているのだと考えています。
今回は、その日本刀を抜く抜刀動作において、どのような事を意識して稽古するかについて、古伝体術流の解説をしていきたいと思います。
まず、古伝体術では「ぶつからない」ということを念頭に置いて稽古しています。
通常は誰もが抜刀するという行為を、躊躇することなく行うことが出来るかと思います。
ですが、その刀を抜こうとしている右手を誰かに抑えつけられた場合は話が違ってきます。
まず、抑えつけてくる相手の力とぶつかってしまい動かすことは容易ではなくなります。
そこで必要となってくるのが
「浮身」
「螺旋」
「等速度運動」
「順体」
などの衝突が消えるための感覚となります。
これらを認識しながら抜刀動作を訓練することによって、抑えつけられた状態でも相手の力とぶつからないで抜刀することが出来るようになります。
その感覚について解説した動画です
抜刀の瞬間に”無限”を宿す―衝突なき世界への道を切り拓く「操り人形」となる感覚とは
古伝体術では、そこを一人稽古と対人の相対稽古によって体得できるようになっています。
~古伝体術の「操られる感覚が導く衝突が消える世界」を体験しま
体験稽古のご案内・お申し込みはコチラから↓
〜1日で武術の秘伝を伝授!?『一触即解!』古伝体術1セミ
1セミナーのご案内・お申し込みはコチラから↓
https://kodennoosie.com/
〜古伝体術公式HP〜
https://kodennoosie.com/